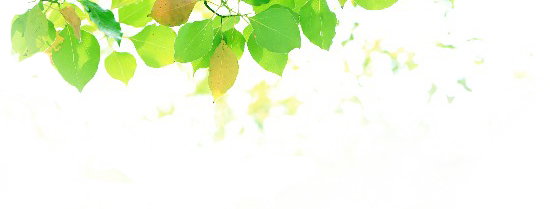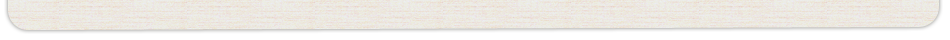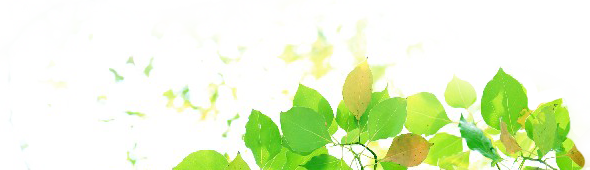遺産分割について(その4)
8月 27日
みなさん,こんにちは。弁護士の福本昌教です。前回2017年3月の投稿(相当昔になってしまいました。)に続き,今回は相続分について,簡単にご説明します。
1 意義
相続分とは,共同相続人の積極財産・消極財産を含む相続財産全体に対する各相続人の持分をいいます。被相続人は,遺言で相続分を決めることができますが,この指定がないときには,民法の定める相続分の規定が適用されます。
2 指定相続分
被相続人は,遺言で指定した相続分です。
3 法定相続分
被相続人による相続分の指定がない場合に適用される民法の定める相続分です。
(1)配偶者相続分の法定相続分
配偶者は,常に相続人となります。
(2)血族相続人の法定相続分
① 第1順位の血族相続人(子)
ア 配偶者と子が共同相続人である場合
配偶者が2分の1,子が2分の1となります。
イ 子が数人ある場合
子が数人であれば同順位で,かつ,均等の相続分を有するのが原則となります。
② 第2順位の血族相続人(直系尊属)
ア 配偶者と直系尊属が共同相続人である場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1となります。
イ 同順位の直系尊属
同順位の直系尊属がいる場合,均等の相続分を有します。
③ 第3順位の血族相続人(兄弟姉妹)
ア 配偶者と兄弟姉妹が共同相続人である場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。
イ 兄弟姉妹が数人ある場合
兄弟姉妹が数人であれば同順位で,かつ,均等の相続分を有します。
ウ 片親のみが同じ兄弟姉妹の場合
半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹とがいる場合,半血兄弟姉妹の法定相続分は,全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
4 相続分の変動
相続分の放棄,相続分の譲渡によって変動することがあります。
なお,遺産分割において,当事者の合意によって法定相続分と異なる分割方法を定めても有効と解されます。次回は,遺産の範囲について,簡単にご説明したいと思います。